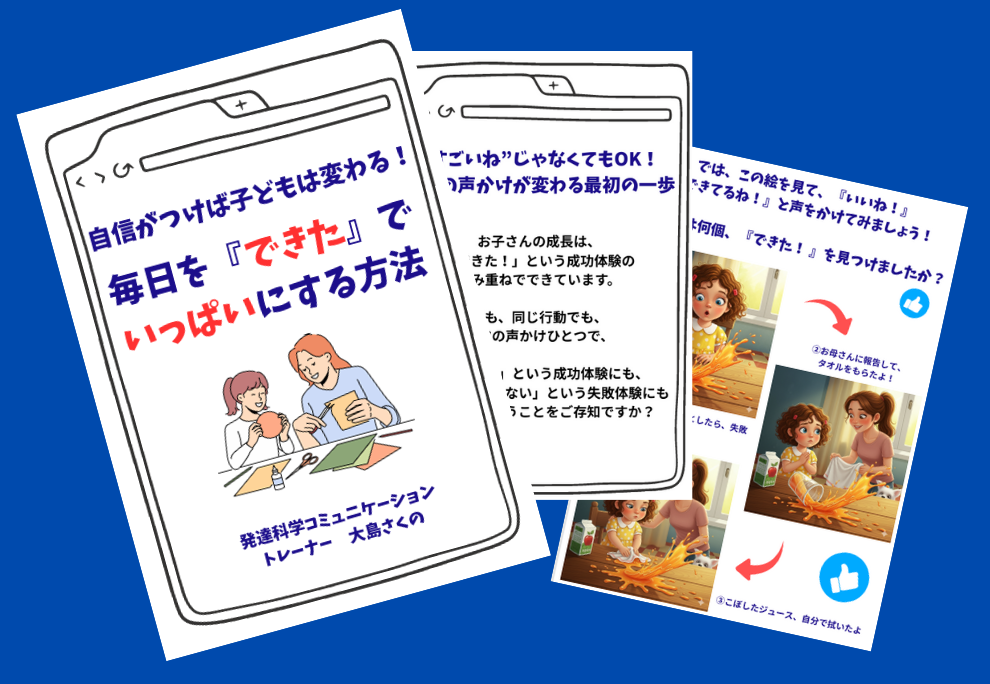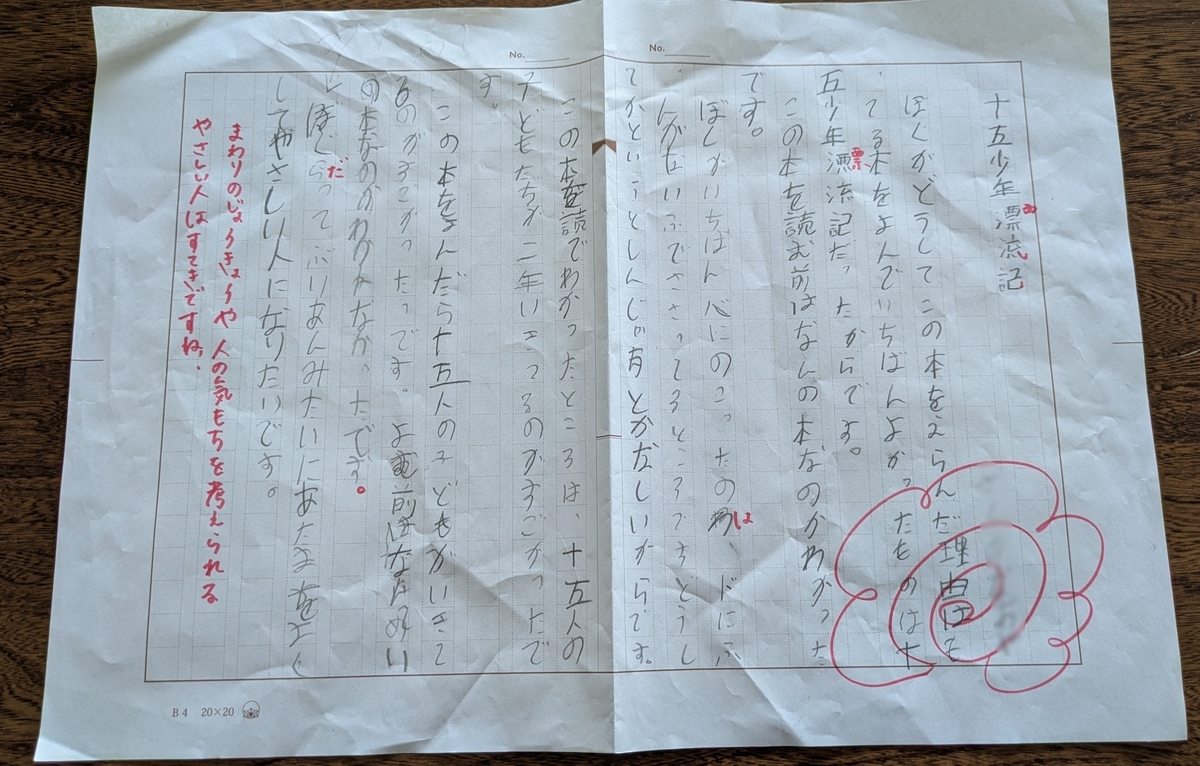こんにちは!
2か月早産で生まれた長男(8)と繊細な次男(5)を育てている
発達科学コミュニケーション・トレーナーの大島です!
今日は「発達検査で見えない困りごと」についてお伝えします。
■この記事でわかること■
-
発達検査では測れない、早産児ならではの困りごと
-
なぜ不器用さが出やすいのか、その理由
-
支援の場がバラバラになりやすい実情と、親ができること

発達検査はしたものの・・・
「発達検査を受けたけど、これで全部がわかるのかな?」
「数値は平均でも、日常生活では困りごとがある…」
そんなモヤモヤを感じること、ありませんか?
検査では見えにくい“困りごと”
発達検査の数値は平均でも、日常では「不器用さ」や「ことばのつまずき」で困ることがあります。
〇不器用さ(早産児あるある)
早産児は、予定より早く外に出たことで、お腹の中で育つはずだった「感覚と運動のつながり」を育む時間が足りていません。
お腹の中は浮力があり、自由に体を動かせます。
でも、外の世界は重力があり、思うように体を動かせない環境。
そのため、体をなめらかに動かす経験が少ないままスタートすることになります。
その結果、
-
粗大運動(走る・跳ぶ・バランスをとる)がぎこちない
-
微細運動(つまむ・ボタンをかける・字を書く)も苦手
といった「不器用さ」につながりやすいのです。
〇言葉のつまずき(吃音など)
長男には「ことばが詰まる」「返答に時間がかかる」という困り事がありました。
これも周囲からは、理解できていないと思われがちな特徴です。
しかし検査結果を見れば「理解力は平均的」だと分かるので、先生には、「考えをまとめるのに時間がかかるようようなので、急かさず、最後まで聞いてあげてほしいです」とお願いしました。
しばらく経ってから、長男のこの特徴は、吃音(どもり。スムーズに言葉が出てこない症状)だと分かったのですが、こういった事は検査結果には出てこないです。
※吃音は早産あるあるではないです※
支援はバラバラになりがち…
実際の支援現場では、施設ごとに得意分野やオリジナルのやり方があったりします。
例えば、
-
運動系のことは施設Aが得意
-
集団でのやり取りは施設Bが得意
-
学習系は施設Cが得意
といった感じ。
また、それぞれの情報も共有されるわけではありませんので、他の施設にも共有したい事(他えば、マンツーマンで指導してくれている施設の先生に、『〇人の集団だった時は、こんな感じでした。』とか)は、私が伝えていました。
つまり、お母さんが全体を見て調整しないと、一体的な支援のつながりがもてないのです。
親の役割も重要ですね!
最後に
発達検査は大事な手がかりになりますが、数値だけでは見えない困りごとがあるのも事実です。
検査自体に詳しくなる必要はないですが、
-
検査で得られた強み・弱みを先生や支援先に伝えること
-
家では自信を回復できる環境をつくること
大事なのは、この2つだと思います。
次回は、「家での環境づくり」について詳しくお話ししますね!